第46回:MySQLからTiDBへの移行に関する技術調査
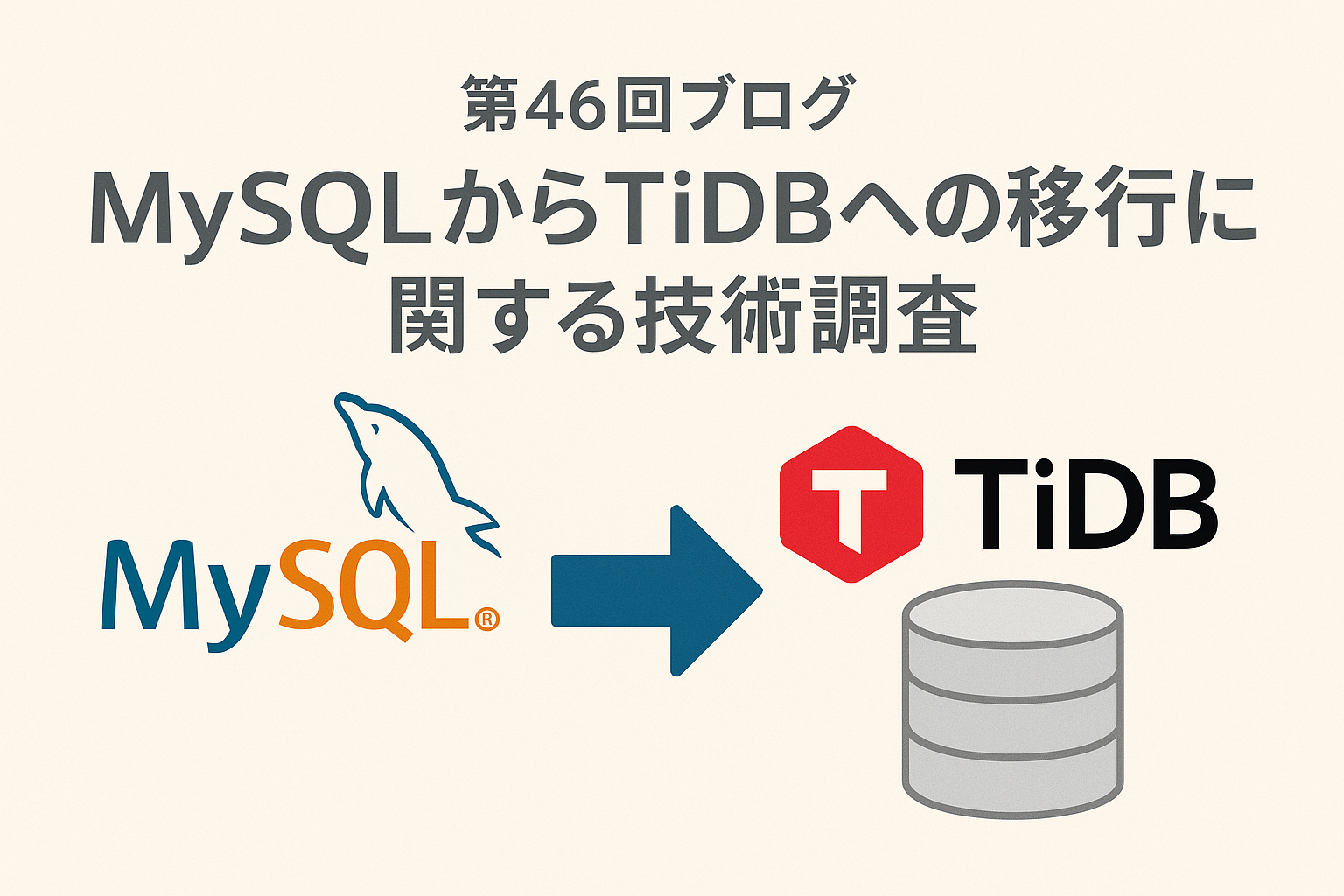
1. MySQLとTiDBの技術的な違い
MySQLとTiDBはいずれもリレーショナルデータベースですが、設計思想・アーキテクチャ・機能面に大きな違いがあります。
TiDBは「NewSQL」に分類される分散型RDBMSで、MySQL互換を保ちつつも、高いスケーラビリティ・高可用性・HTAP(Hybrid Transactional/Analytical Processing)対応を実現しています。
| 項目 | MySQL | TiDB |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | 単一サーバ中心。SQL/ストレージ一体。主に垂直スケール。 | SQLノード・分散KVS・メタ管理が分離。完全分散・水平スケール。 |
| スケーラビリティ | 基本はサーバ増強(垂直)。シャーディングには手動運用が必要。 | ノード追加で自動シャーディング・自動リバランス。数百ノードまで拡張可。 |
| トランザクション | 単一ノード上でACID保証。分散トランザクションは非ネイティブ。 | 分散ACIDをネイティブサポート。クラスタ全体で一貫性保証。 |
| SQL互換性 | MySQL独自拡張含むフル機能。SP/トリガ/外部キー等も対応。 | MySQL 8.0互換。多くのツールが利用可。SPやトリガは未対応部分あり。 |
| HTAP/分析 | OLTP特化。大規模分析は外部DWH/OLAPで処理が一般的。 | HTAP対応。TiKV(行指向)+TiFlash(列指向)で即時分析が可能。 |
| 高可用性 | レプリカやクラスタで実現。手動フェイルオーバー・運用負荷あり。 | Raft自動レプリケーション+自動フェイルオーバー。自己回復型。 |
| クラウドネイティブ性 | 単一サーバ前提。近年はRDS等のマネージド型も。 | Kubernetes公式サポート。クラウドネイティブ設計・Serverless型有。 |
補足:TiDBは自動シャーディング・リアルタイム分析・高可用性・クラウド運用等でMySQLの弱点を補う一方、ストアドプロシージャなど一部未対応機能や分散処理によるレイテンシ増などのトレードオフも存在します。
ユースケース・既存資産との相性を見極めて選択する必要があります。
2. TiDBが開発された背景・目的
TiDBは中国PingCAP社により開発された分散型RDBMSです。開発思想はGoogle SpannerやF1論文の影響を受け、「SQL互換・自動シャーディング・高可用性・リアルタイム分析・クラウドネイティブ運用」の実現を掲げています。
手動シャーディング運用やMySQLのスケール・可用性の壁、分析DBとの煩雑なデータ連携といった、現場の課題を根本から解決する“Webスケール”な新世代RDBMSがNewSQL=TiDB誕生の背景です。
- スケーラビリティ:クラスタでリニアな拡張性を追求
- 運用負荷軽減:自動シャーディング・レプリケーションでDBA負担減
- HTAP統合:OLTP+OLAPを単一基盤で両立
- クラウド適合:K8s等の自動化環境に最適化
- MySQLユーザの資産活用:プロトコル互換で既存アプリを容易に移行可
3. MySQLからTiDBに切り替える必要性と判断基準
どんなときにTiDBを選ぶべきか? 技術的・運用上の判断ポイントを整理します。
- 膨大なデータ量/トラフィック:数百GB~数TB超の肥大化・高QPS環境ではMySQLの垂直スケールに限界。TiDBならシャーディング不要で拡張可。
- 高可用性/障害耐性:24h無停止やマルチAZ/リージョン運用。自動フェイルオーバーやDR、自己回復能力が必須なシステム。
- シャーディング運用が困難:シャード間JOIN・整合性・アプリ改修コストが重い場合。TiDBならアプリは単一DBとして利用可。
- HTAP/リアルタイム分析ニーズ:分析用クローン不要。TiFlash連携で本番データの即時集計が可能。
- スケールアウト/メンテ負荷:ノード追加・大規模DDLがダウンタイムなしで実行可能。定期メンテによる開発ボトルネックを解消。
- 将来的な成長・戦略的判断:ユーザー・データの急増が想定される新規事業。最初からスケーラブル基盤で始める戦略。
- 機能互換性:ストアドプロシージャ・トリガ・外部キー等MySQL独自機能の利用状況も要チェック。シンプル構成なら移行は容易。
MySQL運用が「つらくなった時」「分割や停止・分析のコストが増大した時」が移行の好機。逆に負荷が小さい間は現状維持も選択肢。
4. TiDBの将来性
- 開発の活発さ:2017年の1.0公開から年1回ペースでメジャーリリース。エンタープライズ利用に堪える進化。
- 新機能:2023~2024年にはベクトル検索やフルテキスト機能が追加。AI/ビッグデータ連携・リアルタイム分析を強化。
- クラウド連携:TiDB Cloud(Serverless/Dedicated)でAWS/GCP上に容易に展開可能。TiSparkやFlink等の分析ツールとも統合。
- 国内外の導入事例増:メルカリ(開発環境)、スクエニ・Cygames等のゲーム、Bolt社(配車・決済)など大規模事例も増加中。
- 運用コスト・経済性:Apache 2.0 OSS。クラスタ運用のコスト最適化・人的負荷削減効果。分析DB不要化によるTCO削減も。
- コミュニティ/サポート:日本国内でも勉強会・事例共有活発。PingCAP日本法人・有償サポートも。
5. 実際の導入事例・成功例・課題例
- メルカリ(開発環境): MySQL複数クラスタのシャーディング→TiDBへ統合。TiDB DMやProxySQL等のツール活用で移行負荷を最小化し、開発効率向上の事例記事がある。。
- オンラインゲーム各社: スケール・可用性・分析ニーズで導入が進行。サーバレス型TiDB Cloudで少人数運用も可能に。移行後、設計やチューニング次第でパフォーマンス改善事例多数。
- Bolt(欧州配車サービス): MySQLクラスターからTiDBへ段階的移行。マルチリージョン・リアルタイム分析やゼロダウンタイムアップグレード実現。
- 教訓・課題:
TiDB向けテーブル設計・クエリ最適化(インデックス設計・統計情報管理等)でMySQLとは違ったノウハウが必要。
チューニングガイドや現場ナレッジの活用が重要。
「合わなければ再びMySQL等に戻す」柔軟な判断も大切。
分散DBの特性理解やチームのスキルアップも必要不可欠。
MySQLからTiDBへの切り替えは、スケーラビリティや運用効率を劇的に高める手段。事前検証や最適化のためのチーム体制も整えて導入を成功に導きたい。
何かノウハウがたまったら、TiDBについてまた書きます。